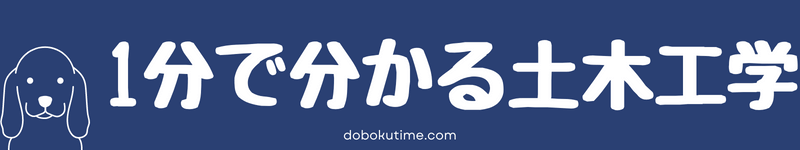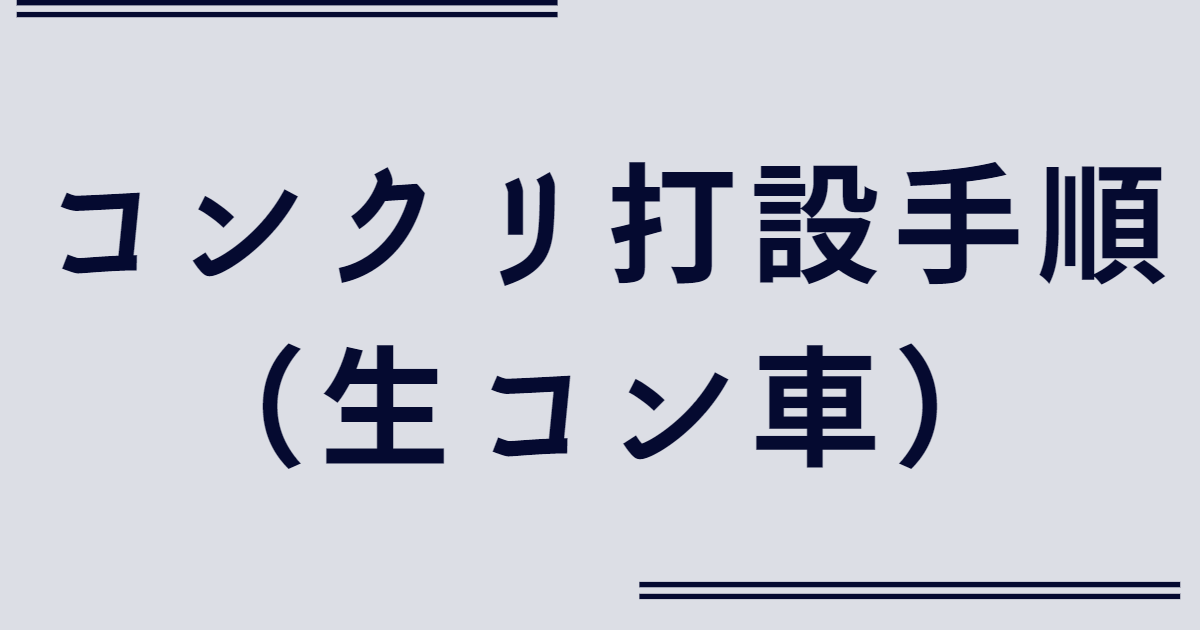生コン打設の仕組み
コンクリートプラント(工場)から生コン車(アジテータ車)が現場に到着し、積んできた生コンをポンプ車へ移し、ポンプ車から配管を通して生コンを打設箇所へ送ります。
(左がポンプ車、右がアジテータ車。株式会社ジュープラスより)
交通計画
コンクリート打設の施工管理項目として、生コン車の交通計画があります。
事前に、生コン車がどの道を通り、どの入り口から現場に入ってくるのかを予め決めておくのです。
生コン車の基本容量は約4㎥です。
一度のコンクリート打設量が300㎥とすれば、通常の交通量に加えて75台以上追加されることになります。
さらに現場に入場するために転回したりうろうろしたりすると交通への影響が大きく、特に都市部ではアジテータ車が渋滞の起点になってしまうこともあります。
そのため、交通への影響が小さいルート、時間帯で、現場へはどの入口から入場するのか、待機場所はどこなのか、等を事前にプラントへ連絡しておく必要があります。
待機場所とは
先ほど、「待機場所」という言葉を出しましたが、生コンを積んできたアジテータ車がポンプ車につける前に待機しておく場所という意味です。
打設箇所に絶え間なくコンクリートを供給し続けるためには、生コン車が間を空けることなくポンプ車に生コンを供給し続ける必要があります。
1台の生コン車の容量を使い切ってからその1台を現場から退場させて、その後新しい生コン車が到着するまで待っていては、打設間隔が開き、コンクリートにコールドジョイントが発生する恐れがあります。
そのため、供給中の生コン車に加え、待機中の生コン車が控えるための待機場所を現場内もしくは現場のすぐ近くに設けておきます。
そうすることで、1台が打設している間、次の1台は待機場所で待機し、1台目が終わるや否や待機中の1台が現場へ入場できるのでポンプ車への生コン供給間隔を狭めることができるのです。
より打設量が多い大規模な現場では、ポンプ車に2台の生コン車が生コン供給を行い、1台ずつ待機車両と交代することで継続的な打設を行います。
ちなみにさらに大きな現場では、ポンプ車を複数台使うところもあります。
都市部でも立坑の底版コンクリート打設であれば、ポンプ車6台で同時打ちなんてこともあります!
生コン車の入退場
生コン車(アジテータ車)の入場や駐車の際には、現場の重機や作業員との接触防止のために警備員(誘導員)を配置します。
常時よりも警備員を増員することになるので、警備会社に予め交渉しておきましょう。
打設当日になって誘導員増員を忘れていて、自ら誘導員も兼任するというのが若手現場監督あるあるだったりします。
受入れ試験
コンクリート打設当日、1台目の生コン車が現場に入場すると、コンクリートの受入れ試験を実施し、合格であれば打設を開始できます。
受入れ試験項目は、スランプ、空気量、塩化物量、圧縮強度です。
気温等も一緒に黒板に書いて発注者立ち会いの下、写真に収めます。
入場した生コン車のシュートからネコ(一輪車)にネコ一杯分の生コンを貰います。
これが受入れ試験分になります。
その後生コン車はポンプ車について打設準備を始めていますので、受入れ試験が合格であれば大きく手で丸を作ってポンプ車に合図しましょう。
同時に、トランシーバーで筒先の現場監督にも試験の合格を伝えて、打設を開始させます。
納品書の管理方法
各生コン車の運転手は納品書(伝票)を持っています。
現場監督は納品書を受け取り、その1台の積載量やプラント出発時刻を確認します。
コンクリートの練り混ぜから打設までの時間が120分(気温25度以上なら90分)と規定されているので、出発時間から計算してあと何分で打設してしまわないといけないのか判断できます。
納品書は打設数量の証明として保管しておきます。
打設数量が多い場合などは、生コン車のドライバーが自分で納品書を留めてくれたりします。
その場合は、ポンプ車の側面にマグネットでクリップを留めておくなど、「ここに留めておいてほしい」ということを分かりやすくしておきましょう。
当日の配車計画
コンクリート打設当日の生コン車の配車において最も重要となるのが、「あと何台生コン車を呼ぶか」です。
打設数量が予定数量ちょうどになることほほぼありません。
それは型枠がたわんだり、現地の細かな傾斜や凹凸など図面では読み取れない要因があるためです。
打設が終わりに近づくと、筒先担当の現場監督は、残り何㎥くらい必要か計算し、生コン車をあと何台呼ぶのか判断します。
これが本当に難しくて重要なんです。
「多めに呼んでおけば足りなくはならないからいいんじゃない?」と思いますが、生コン車が積んできたコンクリートは、使わなかったとしても、運んできた分だけお金を請求されます。
金銭的にも環境的にも残すのは良くありません。
新入社員がこの判断を任せられることは少ないですが、私がよく言われていたのは、「この判断で1㎥以上誤差を出してはいけない」です。
筒先担当じゃなくてもぜひ一度、筒先に行って見て、残り何㎥かなと自分の中で計算してみてください。
以上、今回はコンクリート打設における生コン車の取り扱いについてご紹介しました。
文章にすると簡単そうに見えてしまうのが悔しいところですが、現場監督を経験された読者の方は「あるある」と共感して頂けるのではないでしょうか。